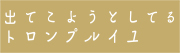::: 対談企画 特別編 :::
上田誠インタビュー2(ネタバレあり)
UEDA MAKOTO
今まで培ってきた財産みたいなことが、全部発揮されたのが良かったです。
──合わせ鏡のように、絵が奥に向かって無限に続いていく「ドロステ効果」を、演劇で表現しようとしたこと自体がチャレンジでしたね。
僕すごく好きな構造なんですよ、再帰的なものが。映像でも何作か作ってますし。たまたま今回、エッシャーに関する資料をあさってる時に、エッシャーの『上昇と下降』という絵を、バッハが作った上り続けるようなカノンと並べて論じてる本があって。それに刺激されて、全体をカノン構造にしようと思ったんです。まず「すぐに議論になる」というシーンを、最初に主題のように入れて、それが何度も繰り返される。さらに中盤からは、サイクロプスが絵から出て来て皆を襲うという、別の旋律が細かく繰り返されるみたいな構造にしました。だから全体的に、カノンのようにずっと繰り返される劇です(笑)。あとは、僕たちが住んでるこの世界が、実は仮想空間である確率がかなり高いというのが、最近ネットとかでまことしやかに語られていて。世界の端っこの方が結構曖昧に作られていて、データ量が減らされてるとか。荒唐無稽といえば荒唐無稽なんですけど、それを「これは誰かが描いた絵の中の世界である」という、今回の世界観に重ね合わせたところはあります。
──実はプレビューを観た時は、サイクロプスの部分はドロステ効果よりもタイムリープなのかと思ったんです。
あー、そうも見えますよね。でも創造主がいないですからね、タイムリープは。今回の場合、俺たちも(この場面の)絵(に描かれた人物)で、この世界の外にそれを描いた奴がいる……という世界なんで。「この世界の創造主が、どこかにいるかもしれない」というシステムの中で、何ができるのかという話だったんです。
──でも本公演では、酒井(善史)さんのメタダイバーからの説明を補足したり、映像を追加したことで、そういう世界であることがかなりわかりやすくなっていたと思います。
それまで(舞台で)やっていた世界は絵の中のことで、その絵が奥の方に追いやられて、場面が変わると一番手前に、その(追いやられた)絵を観ている人たちがいる……という構造を示すには、映像を使うのが一番いいなあと思ったし、大見(康裕)さんは長年一緒にやっている人なので、いい感じに作ってもらえました。あと『(建てましにつぐ建てまし)ポルカ』の怪物とかの特殊造形をずっと担当してる中子(中川有子)さんには、サイクロプスやガーゴイルを作っていただいたり、角田(貴志)さんは絵が描けるから絵を全部監修・作成してもらおうとか。やっぱり今まで培ってきた財産みたいなものが、全部乗せじゃないけど(笑)、発揮できたのが良かったんじゃないかと思います。
──中でも角田さんの存在が、今回かなり大きかったのではないかと思います。外注で描いてもらうのと、劇団員が描くのとでは、やっぱり大きな違いがあったのでしょうか?
外注だと、仕様をきっちり決めてからオーダーしないといけないけど、角田さんとだったら「エチュードで使いたいから、何となく描いてみてください」みたいな、ほわっとしたオーダーができるんです。たとえば、出てこようとしてるペガサスを観て盛り上がる場面を思いついても、それが本当に面白いかどうかを探る時に、やっぱりペガサスの絵を観ながらでないと検証できないなあと思うので。
──ああ、ヨーロッパ企画の場合だと、エチュードで盛り上がらなかったらその絵はボツになるという危険がありますよね。
そうなんですよ。良かったら使うけど、ダメだったらお蔵入りということがあるので、おいそれと外注ができない。だから内部の人に、割と気楽に仮道具を作ってもらえることが、意外と大事なんです。角田さんがいなかったら、この劇はできなかったと思います。
──その角田さんが終盤で、サルバドール・ダリという実在の画家の役で出てきたのはビックリしましたが、彼をキーパーソンにしたのは?
ダリもダブルイメージというだまし絵に近いことをやってるし、ちょうどあの時代のパリで活躍してたし、有名な柔らかい時計の絵も何かに使えそうだったので「ダリは絶対登場するだろうな」とは思っていました。だから「誰がダリをやるんだろう?」というのは、ずっと劇団内で話題になってて(笑)。この構造を内側から壊せそうなぐらいの変性力があって、最後にちゃんと画家と芸術の話ができるというキャラクターは、やっぱりダリしかいなかったですね。
──画家と言えば、永野(宗典)さん演じる老画家が日記を朗読するシーンは、アーティストの宿命的な哀愁を感じさせるだけでなく、これから始まる世界のヒントをさりげなく投げかけるという、大変絶妙なシーンでした。
画家が出てきて直接日記を読むって、最初はちょっと禁じ手のような気がしたんですけど、ピエールが日記を閉じて「ここから先は(部屋にいる登場人物たちに)読まれていない部分ですよ」という所を、永野さんが惰性とか勢いで読み続けるというのは面白いんじゃないかと思いました。その読まれていない最後の数行は、あの人たちの目には触れてない……要は現実の世界に、一度も触れてない言葉なんです。それが紐解かれてしまうような空気感は何となく出ていたと思いますし、しかもあの場面がだまし絵の世界が始まるトリガーというか、スタートの号砲を鳴らす役割みたいな感じにもなりましたね。
宇宙の法則を引き寄せるような変性力が、最近気になっているところです。
──だまし絵を「こんなの子どもだましだ」と言われて画壇から認められなかった画家と、演劇界におけるヨーロッパ企画の立場って、結構似てるんじゃないかと思いましたが。
でもまあ、確かに重ねた……って言うと、ちょっとカッコ良すぎますけど。僕(岸田國士)戯曲賞をもらって、もちろんむちゃくちゃ嬉しかったんですけど、すごく変な話「この宇宙は合ってるのか?」とも思いまして(笑)。大学に受かった時もそうなんです。100%落ちると思ったのに合格通知が来て、嬉しいと思う前に「え? 変なの」って。つまりだから賞をもらってない、あるいは大学に落ちてる人生も同じぐらいの確率でありえて、そうなってても何の不思議も不自由もなかっただろうなという。それって多分、パラレルワールドの考え方なんですよ。どのパラレルワールドにいても、自分は恐らくこういうことをやってるだろうという強い現実と、もしかして一個食い違っていたらそっちはなかったかもという弱い現実があるという。だとするとこの劇の不遇の画家も、一個何かが食い違ったら「すげえすげえ」ともてはやされる世界があったんじゃないか? って考えてたんじゃないかと思うんですね。モノを作る人には、そういうところがあるという気がします。
──ああ、ゴッホとかもちょっと世間の見方が違ってたら、生きてるうちに売れっ子になっただろうにとか、先鋭的なクリエイターにはそういう「もしも……」が付き物ですね。
僕もやっぱり、自分の作りたいモノを作ってるっていう気持ちはあるし、面白いモノを作ってる自信もある。でもそれが「何でこんなに流れが来ないんだろう。このまま誰にも見つからずに消えていくんかなあ」という時期もあれば「うわー、上手く流れが来て良かったー」という時期もあるんですね。そのどっちの気持ちもすごくわかるというのは、あのトロンプルイユの画家と重ねたかもしれないです。
──でも「自分の信じたことを続けていればいいことがあるよ」というありがちな結論には行かず、芸術論の中でふわっと終わる感じが「らしいなあ」と思いました。
そうなんですよ。続けてさえいればいいというわけでは多分なくて、やっぱり売れようとした分だけ売れることってきっとあると思いますし、そこに引き寄せるための法則とかもあるんじゃないですか? それって「この宇宙はどうなってるんやろうな?」みたいな感じに近い(笑)。
──じゃあ極論すると、今回はある種の宇宙の法則を書いた、みたいな。
それはすごくありますね。本人の努力いかんに関係なく、宇宙は進んでいってる……みたいなのが、あんまりそう思えなくて。ダリがまさにそうなんですよ。「天才を演じたら天才になれる」とか「自分でヴィジョンをちゃんと描いて生きていれば、そういう風に世界は変性していく」みたいなことをすごくアジテートしていて、実際にその法則を引き寄せてるように見えるんです。なるほど、もしかして強い芸術家って、そういうことなのかもしれへんなあって。そういう変性力は、ちょっと最近気になっているところです。
──今回も『来てけつ……』もそうでしたけど、最近は割と明るい感じのラストが続いてますよね。
そうなんですよねえ。何となく画家が消えかけた命の中で、一人さびしく……みたいな最後になるのかなあと想像してたんですけど。実は『来てけつ……』も、最初は(主人公の)マナツちゃん以外はみんな機械化した世界になる、みたいな話になると思ってたんですよ(笑)。でもやっぱり劇をさびしく終わると、なかなか辛いところがありますからね。今回のラストでいうと、モナリザが(絵から)出てきて芸術を語りだすというのは、我ながらすごくいいなあと思いました。やっぱり絵画とか音楽って、昔の人が作ったものでも、時を越えて語りかけてくるような感じがあるじゃないですか? それって文字通り「時空を超える」ということで、そういう感覚は入れておきたいなあと思っていたし、そういう終わり方にできたと思います。
──この作品をステップに、今後考えていることはありますか?
今回の劇がまさにそうなんですけど、消費の速いテレビドラマで求められるようなテンプレート的なこととは、これからどんどん乖離(かいり)していけるんじゃないかなあと。こういう珍しい劇を作るのに、割といろいろ突破できる状況ができ上がってきた感じがするんです。たとえば映像の人もそうだし、造形の人もそうだし、役者さんもそう。いろんなジャンルから壁を超えて来てくれる人がそろい始めたので、何か演劇の型にもはまらず、さりとてお笑いの型にもはまらない、面白そうなことがこれからでき始めるんじゃないかなあと。だからあまり簡単なことには落ち着かず、もっと珍しいことを模索していけたらなあと思います。来年は劇団20周年でお祭り的なことをやろうと思ってますけど、21年目からどうするか……今のところ、香港の話をやろうかなと考えてます(笑)。
文:吉永美和子
撮影:清水俊洋