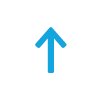──次々に違うフロアが現れる様を、演劇の舞台でどう表現するのか? と思ってましたが、ただ階数表示を変えるだけで同じ舞台を使い続けるというのは、相当な荒技でしたね。
本当にそうなんです。「何で今まで、誰もこうしなかったんだろう?」って思ったんですけど、やっぱりちょっと間抜けだし、カッコいい劇にはならないんだろうなあと(笑)。
──実際数字が変わった瞬間に、客席から笑いが起きてましたし。
そこが一番よかったです。劇団全体でふざけにかかったということで、お客さんも「ふざけられた!」って感覚になったんですかね? でも単なる悪ふざけではなく、誠心誠意、丁寧にやっているつもりなんですよ。あの階数表示も、モニターや電光掲示の方が楽なんですけど、やっぱりどんでん返しじゃないと、あの面白さは出ない気がします。
──確かにどんでん返しの方が、一手間かけてる感じが伝わりますね。
そうそう。スタッフが張り付いてるんだなあ、って。ちなみにあれは本多くんが回していたりもします(笑)。でも「企画性コメディ」って言い続けた効用が、役者…というか、劇団全体に出てきましたね。劇の力点がじょじょに、仕掛けの方に向かってきたという。もちろんお芝居もちゃんとするけど、稽古に入るとどうしても演技の方に気持ちが向くから、放っておくと企画性が二の次になりがちなんですよ。でもここ最近は、全員が企画性をおろそかにしないという、劇団風土ができてきたなあと思います。
──一部のフロアは静止映像で見せて、お客さんにその様子を想像させるという仕掛けも、美術に負けずナイスアイディアでした。
費用対効果などの問題で実現できなかったアイディアは、映像に落とし込みました。でも映像はね、今後ヨーロッパ企画の大事なセクションにしたいんです。というのも『前田建設ファンタジー営業部』で、映像と演劇の掛け算の仕方を追求して、今後さらに広がっていく世界だという予感がしたので。演劇での映像の使い方って、まだそんなに確立されてないって感じがしませんか?
──確かにほとんどの人が、まだ探り探り使ってるという雰囲気ではあります。
照明とか音響の効果は、長年の歴史の中でだいたい確立されてきたと思うんですが、映像はまだこれからだと思うんです。もしかしたら、ものすごい石油が眠ってるんじゃないか? というイメージがあります(笑)。
──ゴールはただ夕日が見える屋上でしかなく、おもむろにそこから引き返すというラストは、観た人の間で賛否両論が出そうだなあと思いました。
今回のラストは、早い段階で「夕日しかない」と決めてたんです。ただあの景色の中で、人間をどう振る舞わせるかについては、結構悩みましたけどね。でも今までヨーロッパって、進まない劇ばっかりやってたんですよ。時代や時間がどんどん前に進む中で、自分たちはここに留まるというような。それが今回は進み続ける劇になって、それがだいぶ苦しかったから、最後は気持よく引き返すのが一番いいだろうなあと。それに、最後までギャグで振り抜くこともできたかもしれないけど、逆に引き返すラストも今回しかできない、という思いもありました。
──でもあの、すごく頑張ったのに最後これだけ? という呆気なさは、ゲームのエンディングを迎えた時の感情にすごく似てましたね。
あ、そうそうそう! ゲームのエンディングって、夕焼けというパターンがすごくあるんで、そういう意味で今回のお芝居にビタっとハマったんですね。でもお芝居のラストとゲームのラストは、やっぱり異質なものなんだなあというのは、今回のちょっとした発見でした。ゲームって物語よりはやっぱりプレイ感覚の面白さのものだから、最後は夕焼けとかで終われるけど、演劇はそうはいかないんだなって。稽古中には、最後にCEOが現れて交渉が始まるとか、勝利の声を上げるとか、何か達成感のある終わり方を考えたりもしたんですけど。
──それはすごく演劇らしい終わり方ですが、結局そうしなかったのは?
まず今の時代的に、そういう前向きな終わり方は、あんまりハマらないかなあと。あと単純に夕日が出て終劇っていうのが、意外と“終”以外の気持ちが出てくることに気づいたんです。『Windows5000』のラストと同じですね。あの何もなくなるラストって、最初は笑いのためにやったつもりだったんですよ。でも実際にやってみると、得も言われぬ寂寥(せきりょう)感が残って「おお…」ってなって。そういう予想外の感情が出てくることって、たまにあるんです。
──斜陽感がただよってきた時代の雰囲気が、今回のラストにすごくマッチしたと。
そうですね。そういうレトロフューチャーへの郷愁みたいなものが、たまたま上手くハマったと思います。あと多分、かなり終盤までイケイケドンドンで進むから、ラストぐらいはウェットなエッセンスがあってもいいかな? という気持ちもありましたね。最後まで仕掛けで走り切るよりも、最後の最後にちょっとソースを加えたい、という感じで。
──あと上田さんが「斜陽の世界」を好んで描くのは、京都育ちであることも関係あるのでは…という話を、公演パンフの中でされていましたが。
どんな大きな帝国でも、終わる時は来ますよね? それこそ今…特に日本やアメリカって、そういう局面が見え始めている気がするんです。そう考えると京都って、昔は日本の中心として繁栄したけど、今はそうじゃないという点で、その状況を先取りしてる…とまでは言えないかもしれないけど、でも都がおわった街、という感じはするんです。京都という場所から世の中を見ると、今の時代はそういう風に見えるってことで。もし僕が…それこそ東京のような「NOW」な場所で生まれ育っていたら、絶対違う劇を作ってたと思います。
──結局はとらえ方や受け止め方が、人によって大きく変わりそうな作品になりましたね。
そうですね。特にあの唐突なラストは、寂寞(せきばく)の中に取り残されたという風に思ってくれてもいいし、「それだけかい!」というギャグとして観てもらってもいいし…どう感じてもらっても、多分着地できるラストじゃないかなあと思ってるんです。一応僕の中では「こう思ってほしい」というモノはあるけど、それはコントロールできないですからね。
──今後の企画性コメディの、可能性を広げたと思える部分はありますか?
「何でこんな劇を作ったんだろう?」って思われるような劇が、やっぱり面白いということですね。たとえば今回なら、メインのチームが問題を解いている時に、下の階から別のチームが呼びかけてくる声が聞こえるシーンって、すごく変なシーンじゃないですか? なんでこんな微妙な気持ちになりながら、三角形の合計数を数えなきゃいけないのかって…ああいう「何やねんこのシーン?」っていう場面が、僕はすごく好きなんです。
──なぜこんな状況に置かれているのかが、誰もよくわからないという。
そうそうそう。現実の生活でも「何でこんなことやってんだ?」っていう時って、たまにあるじゃないですか? それってやっぱり、あることの「途中」の状態なんですよ。そういう時間が僕はやっぱり愛しいし、大切にしたい。だから今後も、何かの途中の状態の時間とか、世界が終わった後もまだ続いてる世界みたいな空間とか…それって決して、世界の中心じゃないんですよね。時間からはみ出た時間、空間からはみ出た空間みたいな、世の中になくてもいい時空間。今後もそれを絶妙な劇にしていきたいと、改めて思いました。
──『インテル入ってない』『Windows5000』『サーフィンUSB』に続く、ITダジャレシリーズでしたね。
もうないかと思ってたら、ありましたね(笑)。でもそんな風に、ダジャレのタイトル一つだけで、これだけの劇が作れたというのは、集団の自信にもなったと思うんですよ。だからより、誰も書こうとしない…「何だこの時空間?」みたいな劇をやっていきたいと思います。
取材:吉永美和子